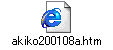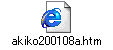|
ヘンリー・ジークフリートソンピアノリサイタル
■2004年12月6日19時〜 東京文化会館
■演奏曲目
1.ショパン ノクターンOP48-1
2.ショパン バラード第4番
3.ショパン ソナタ第2番
4.リスト ソナタ
5.リスト「ドンジョバンニ」の回想
以下アンコール
6.シベリウス”樅の木”
7.シベリウス”フィンランディア”
8.ショパン 華麗なる大円舞曲(第1番)
ノクターンのはじめのフレーズを聞いたとき、あまりに魅力のあるピアノの音に心が洗われる思いでした。あまりに綺麗な響きと語りかけるような表現。
ピアノが打楽器であることを忘れさせられる瞬間がそこにはありました。
これは、デルモナコがビロードの声を持っているような、そんな比喩が最も合っているのではないか、とヘンリーさん持っている「音」に対し感じるのでした。
また非常に息の長いフレーズを音楽が途切れることなく、場合によっては1ページ以上の長い旋律までも気持ちを切ることなく練り上げる部分には音楽を切りたくない大切にしたいという気持ちを痛いほど感じました。
かつてサンソンフランソワがそのような長いフレーズをよく弾くことがありましたが、そのような大胆な挑戦はなかなかできないものだと感じています。
また、瞬間瞬間の気持ちを大切にすることから気持ちのゆれが微妙なリズムの揺れとなったり表現の揺れとなって表れる様子は大家の風貌を備えているとさえ感じる部分がありました。
それらの長いフレーズや微妙な表現、それら全体を納得させる構成力が重要となってきますが、そういう点でリストの演奏はあまりに立派で説得力のある演奏だったと思います。特にソナタが絶品でした。
リストの場合、どうしても技術的に華やかな面が強調され、ビルティオーゾとしての面を強調する演奏が多いものです。
特にソナタとなるとまくしたてるような演奏も少なくありません。
そういう中1930年代のホロビッツの研ぎ澄まされた演奏はこの曲の理想的な唯一の解釈だと長いこと確信を持っていました。
華やかさだけを求めるまくし立てるような演奏でもなく、刃物を突きつけられるような極限的な緊張感を求めた演奏でなく、そこにはとても優しい暖かいもので満たされており、そんなこの曲を聴くのは本当に初めてで非常に満足度の高い納得させられる演奏だったと感じました。
始めのGのユニゾンを聞いた瞬間にそこに何か違和感を感じたのです。
技術や精神性ではない何か別のもの「優しさ」とでも言うもの、それが前面に出ていることへの意外さに戸惑ったのですが、全曲聴いて本当によく理解できました。とても説得力のある演奏だったと感激しました。
アンコールの、樅の木とフィンランディアはもうさすがとしか言いようがありません。溢れる音楽がそのまま形となり心の深いところで感動がありました。
あまりに良かっただけに、ここでアンコール終わっても良かったです。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
1.曲の繋がりについて
ノクターンからバラードへ気持ちを続けた演奏をされた点、非常に自然でしっくりと捉えることができ、その気持ちの連続感に心地よさを感じるた。
遺作の方がよかったのかどうか、ヘンリーさんも迷った末の選択だったのだろう。
ただ、バラード4とソナタ2を続けたのはちょっとやりすぎでは。
音楽の盛り上がりという観点では違和感ないものの、表現しているものの質があまりに異なることから気持ちの中にねじられるものを感じざるを得ない。
バラードの方がより心の内面を表現しているところからこの今日の順序そのものにも疑問がある中繋げるとそれが強調されこのような気持ちになったのだと感じる。
2.ノクターン
終始語りかける旋律とあまりにきれいな音(どうして同じピアノであれだけ響きが綺麗なのかわからない。ペダリングや音のタイミング、バランスなどに秘密があるのだろうが本当に感激する。強い音が綺麗なピアニストはたくさんいるが、通常の音(スケールや三度やトリルなど)にあれだけ魅力を感じるピアニストには滅多に出会わない))で奏でられる甘美な旋律は非常に価値の高いもの。
ただ表現があまりに直線的でドラマ性に乏しいところが惜しい。
最後のペダルの切り方が惜しかった。
3.バラード4
音は綺麗なのだが音楽がもっと流れてほしい。
特に前半部分。
流れる音楽の中に、その上で迷い、影が欲しい。
もっとしっとり音楽を聞かせて欲しい。
リズムをずらしたりテヌートをつけたりする部分で必然性が感じられないところがあった。
しかし音が本当に美しく特に内声と絡まった時その響きは絶妙。
白夜のピアニズムといわれる所以なのだと確信する。
これは全体的な傾向だが、長いクレッセンドのフレーズで途中アッチェレランドをかけて最後ritして収める弾き方が多く納得感がない(以降表現Aと呼ぶ)。
全体として何を表現したいのかわからない。その場その場の表現に終始している感あり。
気持ちが入り込みすぎてリズムが甘くなるところが気になる。
コーダ(atempo)の前の和音の部分、先の表現Aが強烈に強調されたところ、気持ちから来る表現とは思うが、あれにはついていけない。
もう少し葛藤迷いなどショパンの微妙な面があっても良いと強く感じる。
4.ショパンソナタ2
(1)1楽章
あまりに直線的。ある意味もっと丁寧な演奏を期待したい。P3への持って行き方はうまい。しかし全体的な構成力が感じられない。
ここでも表現Aが随所に出ておりその際リズムがずれる時非常に気になる。
最後の部分はバラードと同様もっと気持ちを大切に大きな演奏を期待したい。
(2)2楽章
急ぐ部分が気になる。落ち着かない。
音楽が平坦でつまらない。
lentoに入るまであまりに一気に持っていくのはもったいない。
もっと微妙な表現が欲しい。
lento部分の旋律は綺麗なのだが、もっと伸びる部分についてもっと表現を大きくして欲しい。そういう部分に物足らなさを感じる。
転調する際の音の切り方がすごくきれい。
細かい音の切り方、響き方など非常に良く考えている。
曲全体として割り切りすぎの印象。
ここでも前述の表現Aの部分が非常に気になる。
こうなると音楽の広がりが無くなり、小さくなってしまう。惜しい。
(3)3楽章
行進部分の表現で、気持ちの高ぶりに伴いリズムがずれるが(フレーズの区切り最後で敢えて付点をなくして八分音符を強調した部分は、そのような校訂版があるのだと理解。ここで言っているのはその部分ではない)、それはそういう自由な直感を重視した感覚的表現と理解する。葬送行進という性格上リズムの揺れは気持ちの表現ある意味描写的表現とも捉えることができるからである。
中間部の長調の旋律の後再度同じ行進部分が現れるがその時は前半に比べると正確さを重視していた。これは感情の整理がついた後の行進という表現という解釈なのだと判断した。
長調部分の音の処理がうまく綺麗。透明感ある音。
緊張感を長く保つ感覚が亜紀子さんの表現に似ていると感じた部分あり。
(4)4楽章
ヘンリーさん独特の甘い優しい表現タッチで奏でる16分音符の繋がりは非常に魅力のあるもの。
しかし感情の起伏はもう少し欲しい。
悲しみを抑えてもついこみ上げてくる感情みたいなものをもっと表現してほしかった。行進の後の一陣の風という描写的表現に終始していた感あり。
5.リストソナタ
冒頭にも書いたように絶品。
何を表現したいか明確。
確信を持った音楽を余りある技術で思う存分表現しているという感じ。
自信が有るので説得力がある。
音のバランスはよく切れもあり、付け入る隙が無い。
技術だけでぐいぐい押すような傲慢なまくし立てるような表現を避けているところに好感が持てる。暖かい演奏。
またきらびやかなところに綺麗な音がフィットして天の声、白夜のピアニストという表現が良く合う。スケールやトリルが綺麗過ぎ。魅力あり。
本当にすばらしい演奏と感じた。
6.ドンジョバンニ
見事に弾きこなしたという印象。
しかしこの曲が恐らく同じ主題を使ったショパンの”ラチダレム変奏曲”を意識して書かれたものであろうが、それとの比較でこの曲自体があまりに音楽的に希薄と感じる。
見事にきれいに弾いてくれたという以上の印象が残らない曲だった。
〜ここからアンコール〜
7.シベリウス”樅の木”
しっとり丁寧に弾かれショパンで感じた違和感を全く感じない。
心に染み入るすばらしい演奏と感じた。
さすが。
8.シベリウス”フィンランディア”
ピアノで表現したオーケストレーションに感激。
色彩感あり。表現力あり。
表現すべきものの骨格が明確なので引き寄せられる。全曲に増してさすが。
9.ショパン”華麗なる大円舞曲”
これはアンコールの予定になかったのでは。
残念ながらこれは弾きべきでなかったと確信する。
あまりに表現が雑でショパンを聞いている印象を受けない。
以上
 |