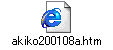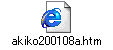|
�R�����I�q�^�w�����W�O�t���[�h�\���s�A�m�f���I���T�C�^�����
�������F�Q�O�O�P�N�W���Q�O���P�X�F�O�O�`
���ꏊ�F�x���f�B�A�[�g�T����
���ȖځF
�@���[�c�A���g�F�s�A�m�\�i�^�j�u�T�Q�P�i�f���I�j
�A���X�g�F����̔N�u�C�^���A�v���
�B�V���p���F�v�������[�h���
�C�V���p���F�X�P���c�I�R��
�D�V���[�x���g���z�ȁi�f���I�j
�E�u���[���X�n���K���[���ȂP�C�T�C�U�ԁi�f���I�j
�����t��]
����̉��t���ʏ�̃R���T�[�g�z�[���ł͂Ȃ����t�҂ƒ��O����̂ɂȂ邱�Ƃ��ł���A�b�g�z�[���Ȋ��ł��������ߋ����Ƃ����ϓ_�ł��Ȃ��a������������Ȃ������B
�T�����R���T�[�g�̏ꍇ�����̗e�ςɑ���l�̑̐ϔ䗦����ϑ傫�����̂ƂȂ�B
�R���N���[�g�ƃt���[�����O�̕����͎c�����������Ă��f�b�h�ɂȂ邱�Ƃ͂��肦�Ȃ����A���ꂾ���́w�l�x���͂���ƒ��f�b�h�ƂȂ�B���̂��ߑS�̓I�ɋ���������Ȃ������̂��c�O�ł���B
���炭���n�[�T���ł͐l�̂��Ȃ��c���̂��镔���Œ������ꂽ���߁A�ɓx�ɉ���}�����s�A�j�b�V���̃��K�[�g�X�^�b�J�[�g�𑽗p���A�܂��y�_�����}���邱�ƂƂȂ����̂ł͂Ȃ����Ɛ�������B
���̊��ł͂����Ɖ����o���܂��y�_���������Ƒ��p���Ă����Ȃ��͂��B���̂��߁A�Ⴆ�V���[�x���g��condelicatezza�Ŏw�肳�ꂽ�����̕����������̉��Ƃ̑Δ�ɂ����Ă��̕����̉��y�I���ʂ��\�������ł��Ȃ����ƂƂȂ��Ă��܂��B���������Ӗ��ł̓��[�c�A���g�A�V���[�x���g�ɂ��Ă��ʏ�ʂ�second�����y�_�������悩�����̂ł��낤�B���������̔��ʁA�Ⴆ��Allegrovivace�̕����ł͂��̑��ʂȉ��F���悭�������A�l�����������F�A���y�������Ɋ����邱�Ƃ��ł����B
���ɔޏ��̏㕔�̐����̌����ȉ��F�͖{���ɖ��͂�����B�\���ł͌����ł��邪���́A�����čׂ��Ȃ��̂ɐ���ł��Đ����͂̂��鉹�͎����Đ��܂ꂽ���̂Ȃ̂��Ɗ�����B���̈���Ō������Ȃɂ��Ă͂悭�v�Z���ꏬ�����̂Ƃ͂��������ȃ_�C�i�~�b�N�X��\�����Ă���B�_�C�i�~�b�N�͂����܂ʼn��̕��̂��Ƃł����ΓI�ȉ��ʂ̂��Ƃł͂Ȃ��B
���F�Ɖ��ʂ����ĕ\���̕�����g���v�������[�h�̂P�U��Q�S�������ɒe���Ă���̂͂܂��Ɉ����B�Q�R�̉��߂͂����܂łQ�S���ӎ��������̂ł���Ɨ�������B
���̂悤�Ȓ��P�Ԃɂ��Ẳ��߂̑_������◝���ł��Ȃ��B����̓V���[�x���g�̎n�߂̎��̕\���ɑ���^��ɋ��ʂ���Ƃ��낪����B
����A���[�c�A���g�̎n�߂̓��������͂��Ȃ茤������Ă�������͂�����B���Y���A���F���ɂ��肬��̃o�����X���ۂ���A�����Ƃ��������悤���Ȃ��B���̉��߂őS�̂ꂵ�Ă����B
�`���ł��q�ׂ������̖��̓��[�c�A���g�ɂ͓��Ɍ�������p�����̂��߂Ƃ�����Ƃ��������̉��߂����y�ƕ������Ă��܂��Ƃ�������ꂽ�������������Ƃ��낪����܂��B
�@
�@ |